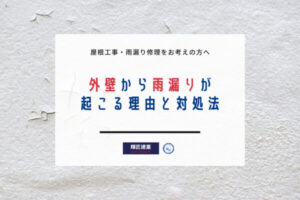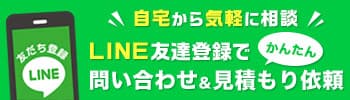新築なのに雨漏りが起きてしまったら…瑕疵担保責任と保証の範囲は?
2023/03/31
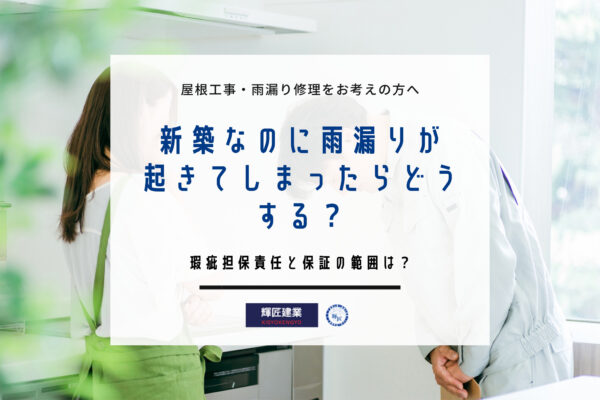
新築で購入したのにしばらくしたら雨漏りが起きてしまう場合や購入してから7年ぐらいで天井から水がポタポタ落ちてきたなど、せっかく購入したのに10年も経たずに雨漏りになってしまうと不安になりますよね。
ただ現在の建築技術では、新築で10年以内に雨漏りが起こるのは考えにくいため、何らかの施工ミスや欠陥がある可能性があると考えられます。また新築には、瑕疵担保責任という制度があり、雨漏りの修繕費や雨漏りで被害を受けた家財についても損害賠償を求めることができます。
この記事では、10年未満の新築で雨漏りが起きた場合の瑕疵担保責任と保証の範囲・注意点などについてわかりやすくご紹介します。
瑕疵担保責任とは

瑕疵担保責任とは、住宅に隠れた欠陥(瑕疵)があった場合に、売主や施工業者が買主に対して負う責任を指します。特に新築住宅の場合、「構造耐力上主要な部分」や「雨水の浸入を防止する部分」が対象となります。これは建物の安全性や居住性に直接関わる部分であり、法律で特に重要視されています。
損害賠償の対象
瑕疵担保責任に基づく損害賠償の対象は以下の通りです。
- 【構造耐力上主要な部分】基礎、柱、梁、壁など、建物の構造を支える部分。
- 【雨水の浸入を防止する部分】屋根、外壁、開口部の建具など。
これらの部分に瑕疵があり、雨漏りなどが発生した場合、修理や損害賠償を請求することができます。ただし、家具や家電など、建物以外の損害は別途火災保険などでの対応が必要です。
瑕疵担保責任期間
日本では「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」により、新築住宅の引き渡しから10年間、売主や施工業者に瑕疵担保責任が義務付けられています。この期間内に瑕疵を発見し、速やかに(発見後1年以内に)通知すれば、無償で修理を受けることが可能です。
適用されない場合
以下の場合、瑕疵担保責任が適用されないことがあります。
・自然災害や経年劣化
地震や台風などの自然災害、または通常の使用による経年劣化が原因の場合。
・新築の定義外の住宅
建築後1年以上経過している、または一度居住したことがある住宅。
・適切なメンテナンスが行われなかった場合
瑕疵が発見された後に放置したり、適切な手続きが取られなかった場合。
施工業者に連絡しなかった場合のリスク
雨漏りなどの瑕疵を発見した際、速やかに施工業者や売主に連絡しないと、以下のリスクがあります。
責任追及の期限切れ
瑕疵を発見してから1年以内に通知しないと、瑕疵担保責任を追及できなくなる可能性があります。
被害の拡大
雨漏りを放置すると、建物内部の腐食やカビの発生など、被害が拡大し、修理費用も増大します。
自己負担の増加
瑕疵担保責任期間(10年間)を過ぎると、修理費用は自己負担となります。
雨漏り発生時の具体的な対処法
以下は雨漏りが発生した場合の具体的な対処法です。
- 早急に施工業者や売主に連絡
瑕疵担保責任の適用を受けるためには、迅速に連絡を取ることが重要です。 - 被害状況の記録
写真や動画で雨漏りの状況を記録し、日時や場所を詳細にメモしておきましょう。 - 第三者機関への相談
施工業者が対応を拒否した場合、国土交通省が認定する住宅紛争処理支援センターや弁護士などの専門家に相談することを検討してください。 - 保険の確認
火災保険や地震保険に雨漏り被害が含まれている場合、保険金での対応が可能です。
保証と保険の違い
瑕疵担保責任は法律に基づくもので、施工業者や売主が負う責任ですが、これに加えて「住宅保証制度」や「保険」の利用も検討してみましょう。
住宅保証制度
施工業者が加入する保険により、万一施工業者が倒産した場合でも修理費用を補填する仕組み。
火災保険・地震保険
建物や家財の損害を補償する保険。雨漏りが自然災害によるものであれば適用される場合があります。
雨漏りが発生する場所と原因

新築住宅で雨漏りが発生しやすい場所は、【屋根】【外壁・サッシ】【ベランダ】の3つになります。それぞれの場所と原因について解説していきます。
屋根の雨漏り
屋根の下には、防水紙による雨水の浸水を防ぐための防水層があります。この防水層があれば雨漏りは起きませんが、この防水層に何らかの施行不良だったり劣化がある場合は、雨漏りが発生する可能性はあります。
また最近ではデザイン重視の屋根が増えてきました。その中でも雨漏りが発生しやすい屋根の種類があります。まずは平面の屋根が特徴の陸屋根は、大雨が降ると屋根に雨水が溜まった状態が長く続き、防水層に少しでもすき間があると雨漏りが発生します。
もう一つは、一方向のみ傾斜が付けられているシンプルなデザインの片流れ屋根です。一枚の大きな板の屋根になりますので雨漏りに無縁そうなイメージですが、片方の雨樋に雨水が集中するため雨水の逆流を引き起こし軒の雨漏りしやすい場所や屋根の裏に水が伝わり、すき間や施工ミスの場所から雨漏りが発生する場合もあります。
外壁・サッシからの雨漏り
外壁やサッシはつなぎ目部分が多いため、サッシの取付けるときに防水テープの間違った貼り方をしていたり、防水加工の施行不良、つなぎ目にすき間が原因で雨漏りが発生する場合があります。また軒がない窓になると直接つなぎ目部分に雨が当たるため雨漏りが発生しやすくなっています。
ベランダからの雨漏り
ベランダの床には防水紙により雨水の浸水を防ぐ防水層がありますが、ベランダから雨漏りがあった場合は防水層の施工ミスが原因になります。そして排水口に枯葉やゴミが溜まりベランダに雨水が溜まりやすくなり防水シートのすき間が原因で雨漏りが発生してしまいます。
また排水口に枯葉やゴミが詰まったままだと雨水の圧力により、排水管の接合部分から雨漏りする可能性もありますので、定期的に排水口の掃除をしましょう。
瑕疵担保責任に基づく修理時のポイント

1. 迅速な対応
雨漏りや構造的な問題が発覚した場合、まずは写真や動画で状態を記録し、速やかに施工業者や売主に連絡を入れることが重要です。このとき、連絡内容や日時を記録しておくと、後々の証拠として役立ちます。
また、応急措置が可能な場合は、二次被害を防ぐために必要な対策を講じましょう。
2. 修理内容の明確化
施工業者との打ち合わせでは、修理箇所や使用する材料、具体的な施工方法について詳細な説明を求めましょう。この内容を文書化し、双方で確認・署名しておくことで、修理範囲や品質についての認識のズレを防ぐことができます。
また、必要に応じて修理前後の状態を写真で記録することも有効です。
3. 修理期間の確認
修理期間については、具体的な工期を確認するとともに、天候や資材調達の影響で工期が延びる可能性も考慮に入れましょう。また、生活に影響が出る場合には、修理中の住環境について業者と相談し、必要に応じて仮住まいや一時的な避難場所を確保します。
特に子どもや高齢者がいる家庭では、健康や安全面を最優先に計画を立てることが大切です。
4. 保証期間の再確認
修理後の保証については、適用範囲や期間、免責事項などを明確に確認し、書面で記録しておくことが肝心です。
また、新たな瑕疵が発生した場合の対応や、その際の費用負担についても事前に確認しておきましょう。場合によっては追加の保証を購入する選択肢も検討できます。
5. 第三者機関の活用
修理内容や費用に納得がいかない場合、国土交通省が所管する住宅紛争処理支援センターや弁護士、建築士などの専門家に相談することで、公正な解決が図れます。
特にトラブルが複雑化した場合には、早めに第三者の意見を取り入れることで、解決への道筋が見えてきます。
また、必要であれば、裁判外紛争解決手続き(ADR)を利用することで、迅速かつ費用を抑えた解決を目指せます。
まとめ
新築住宅で雨漏りやシミ・カビなどの不具合を見つけた場合は、すぐに施工会社へご連絡いただくことをお勧めします。早めに対応することで、被害の拡大を防ぐことができます。
特に重要なポイントとして、瑕疵担保責任による保証を受けるためには、不具合の発見から1年以内に施工会社への報告が必要です。この期限を過ぎてしまうと、適切な補償を受けられない可能性がありますので、できるだけ早めのご連絡をお願いいたします。
また、補償請求の際の大切な証拠となりますので、雨漏りの跡やカビの発生状況、天井や壁面のシミなど、被害状況はできるだけ詳しく写真に残しておくことをお勧めします。
エーストラストでは、雨漏り診断士の資格を持つ専門スタッフが、最新の技術と豊富な経験を活かし、屋根の状態を丁寧に調査・確認させていただきます。その上で、建物の構造や状態に合わせた適切な修理プランをご提案いたします。
確実な修理を心がけておりますので、大阪府で雨漏り修理をお考えの方は、小さな症状でもお気軽にご相談ください。経験豊富な専門スタッフが、丁寧にサポートさせていただきます。